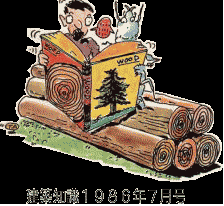| 目で見る建築木材カタログ | |
 1.杉「スギ」 国産・針葉樹・スギ科 日本固有の針葉樹で、ヒノキと並んで建築用材の代表樹種といえる。本州北部から屋久島にかけて分布し、また各地で多く植林されている。屋久杉、秋田杉、吉野杉、天竜杉などは銘木として知られる。 辺心材の境は明らかで、辺材は白色、心材は淡紅色〜暗赤褐色、ときには黒褐色。木理は通直、軽軟で脂気少なく、特有の香気がある。 構造、造作、建具など建築全般、家具、桶樽、下駄など広汎に用いられている。 |
 2.檜「ヒノキ」 国産・針葉樹・ヒノキ科 関東以南の本州、四国、九州に分布する。杉(スギ)とともに日本で最もよく用いられる建築材である。特に木曽材、吉野材は高級品として人気が高い。 辺心材の境ははっきりしないことが多く、辺材は淡黄白色、心材は淡黄褐色〜淡紅色。木理通直、軽軟・緻密で特有の芳香と光沢をもつ。弾力・靱性があり、加工性・耐久性にすぐれる。 |
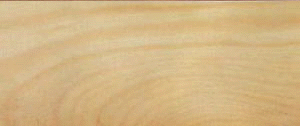 3.赤松「アカマツ」 国産・針葉樹・マツ科 雌松(メマツ)とも呼ばれ、本州,四国、九州に分布。性質が類似し、同様に用いられるものに黒松(クロマツ=雄松)がある。 辺材と心材の区別はあまり明確でなく、辺材は淡黄白色、心材は帯黄淡褐色。樹脂成分が多く、縦断面でヤニ条が認められる。 やや重硬で木理は概ね通直、肌目は粗。小屋材、梁材、床板、根太などに用いられる。 |
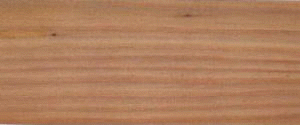 4.唐松「カラマツ」 国産・針葉樹・マツ科 落葉樹(カラマツ)とも記されるように落葉針葉樹である。本州中部の高山地帯に自生するが、近年はたの寒冷地や北海道にも植林されている。 辺材は白色、心材は褐色を呈す樹脂成分が多く,縦断面でヤニ条が認められる。 針葉樹の中では割れ、狂いが生じやすいので現場では使いにくい。産地ではヤニ抜きや、人工乾燥、集成するなどして普及に努めている。 |
 5.米杉「ベイスギ」 輸入・針葉樹・ヒノキ科 アメリカ・カナダの国境地帯を中心にアラスカ南部からカリホルニヤ北部、およびロッキ−山脈に分布する。スギと称されるが、ヒノキ科に属する。 辺材は白色に近くせまい。心材は赤褐色〜黒褐色。材の性状は軽軟で木目は通直、肌目はやや粗。特有の芳香がある。耐久性にすぐれ、下地材、造作材全般に使われるが、国産スギほどの味は出ず、日焼けすると木目もわかりにくくなるほど暗褐色化する。 |
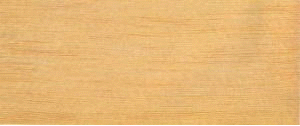 6.米松「ベイマツ」 輸入・針葉樹・マツ科 カナタのブリテイッシュ・コロンビアからカリフォルニァにかけて分布する。ロッキー山型と太平洋岸型があり、前者の法がやや軽軟で目がつみ、和風の造作材としても充分使用できる。 産地により色も変化する。 辺材は淡木白色〜帯赤白色、心材は黄褐色〜橙赤色〜赤褐色。 やや軽軟で木理は通直、肌目はやや粗。樹脂成分が多い。構造材,下地材、造作材など建築全般に用いられている。 |
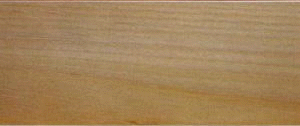 7.檜葉「ヒバ」 国産・針葉樹・ヒノキ科 ヒノキアスナロとも呼ばれ、翌檜=楮(アスナロ)の変種である。北海道南部、本州北部に分布し、都国日本三美林のひとつである青森ヒバはよく知られる。材の性状はアスナロとほぼ同様で、辺材は帯黄白色、心材は淡黄色。辺心材の区別はやや不明瞭。軽軟で木理は通直、葉だ目は蜜。樹脂成分が多く、特有の匂いが有る。構造、造作など全般的に使用され、とくに水廻りで多用される。 |
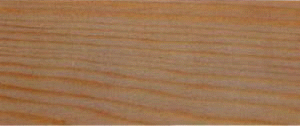 8.栂「ツガ」 国産・針葉樹・マキ科 関東から九州にかけて分布。心材は淡褐色で、辺材は心材より淡色。心辺材の差は明らかでない。やや重硬で、木理は概ね通直、肌目は粗。耐久性はあるが加工性がやや難で、比較的あばれる材といえる。柱、土台,根太、床板、敷居、鴨居など構造材、造作材の全般にわたって用いられる。一時、米栂材が檜材にかわって柱などに使われたため、栂は安物という世評が広まったが、 杢目が優しく、味の有る材である。ただし、ヤニ条にはしばしば泣かされる。 |
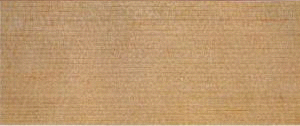 9.米檜「ベイヒ」 輸入・針葉樹・ヒノキ科 アメリカオレゴン州南部からカリホルニヤ州北部にかけて分布。辺材は白色〜淡黄褐色。国産の檜に似た強い芳香がある。国産檜の供給減、高価格化により、単なる代替材として以上の存在となりつつある。やや軽軟で木理は通直、肌目はやや密。土台、柱、床板、造作、建具、家具などに使用される。 |
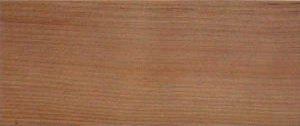 10.米栂「ベイツガ」 輸入・針葉樹・マツ科 アメリカ北西部からカナダ南西部にかけて分布し、ウエスタン・ヘムロックの通称をもつ。同種の者にイ−スタン・ヘムロック(カナダツガ)がある。辺材と心材の区別は明らかでなく、材は帯桃白色〜淡黄色を呈する。やや軽軟で木理は通直、肌目はやや密。加工作性はよいがやや割れやすく、保存性もあまり高くない。柱、鴨居、長押、土台、箱材、桶材、家具、屋根板などに用いられる。 |
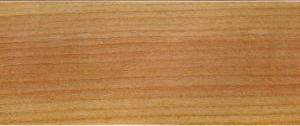 11.シトカスプル−ス 輸入・針葉樹・マツ科 国産の唐檜(トウヒ)あるいは蝦夷松(エゾマツ)と同種で、米トウヒとも呼ばれる。北米大陸西海岸沿いにアラスカ南部からカリホルニア北部にかけて分布する。辺材と心材の区別は明らかでなく、材は白色〜淡黄褐色を呈す。やや軽軟で木理は通直、肌目は密。造作材全般、建具、家具、楽器などに用いられる。針葉樹ではあるが、材質感が安定し、和風の造作材としても充分に対応できる。 |
 12.欅「ケヤキ」 国産・広葉樹・ニレ科 本州、四国、九州に分布。辺材と心材の差は明らかで、辺材は淡黄褐色、心材は黄褐色〜帯黄紅褐色。横断面に春材の大きい導管孔が年輪の内境に沿って配列する、いわゆる環孔材である(クリ、ナラ、タモも同様)。材管は重硬、強靭で肌目は粗。加工性はやや難だが、耐久性はすぐれる。時に木理の乱れによる美麗な杢目を形成し、加輪杢、玉杢、鶉杢、牡丹杢などと呼ばれる。構造材、造作材全般、楽器、臼、杵などに用いられる。 |
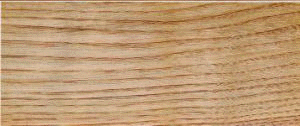 13.栗「クリ」 国産・広葉樹・ブナ科 果実採集のために植栽されることも多く、全国に分布している。辺心材の境は明らかで、辺材は褐色を帯びた灰白色、心材は褐色。材質は堅硬で弾力も大きく、割裂しやすい。耐久性はきわめて大きく。水湿にも強いが、加工性、乾燥性は難である。肌目は粗。土台、水廻り、家具、鉄道枕木などに用いられてきたが、最近では供給量が減り、建築材としては一般的でなくなりつつある。欅などと同様に、漆仕上に適している。 |
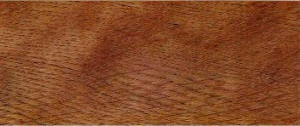 14.水楢「ミズナラ」 国産・広葉樹・ブナ科 ナラ材は広葉樹材として最も重要な者の一つであるり、ほかにコナラ、カシワ、クヌギなどがある。建築でナラというときは概ねミズナラを指す場合が多い。全国に分布する。辺心材の区別は明らかで、辺材は淡紅を帯びた白色、心材はくすんだ褐色。柾目面でいわゆる虎斑といわれる紋様を呈する。重硬で肌目は粗。加工性は難。床板、家具、桶樽などに用いられる。日本での一般材としての利用の歴史は浅く、北海道では高級家具材としてヨ−ロッパへ輸出していた。 |
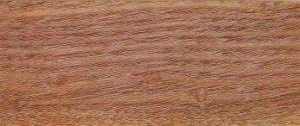 15.谷地ダモ「ヤチダモ」 国産・広葉樹・モクセイ科 北海道から本州北部にかけて分布。近い樹種にシオジ、トネリコ、アオダモなどがある。辺材は淡黄白色、心材はくすんだ褐色で辺心材のくべつは明らか。やや重硬で靭性、弾力に富む。木理は、通直、肌目はやや粗。造作材、家具、器具、合板、運動具(野球のバット、ラケット,スキ−など)などに用いられる。とくに家具材としては、その素直な目が認められ、和風住宅にも利用されている。 |
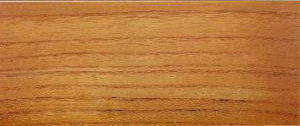 16.山桑「ヤマグワ」 国産・広葉樹・クワ科 全国に分布する。クワ科にはマグワ、ササグワなどがあるが、建築でクワというときは概ねヤマグワを指す。辺材は淡黄色、心材は黄色を帯びた濃褐色で辺心材の区別は明らか。座資質は重硬で靭性があり、耐久性に富む。木理は不規則。床柱、床板などの装飾材、造作材、家具、鏡台、楽器、彫刻材などに用いられる。とくに襖の引手としての利用が一般的で、日焼けすると黄色味が消え、味のある飴色になる。 |
 17.山桜「ヤマザクラ」 国産・広葉樹・バラ科 概ね全国に分布するが、本州中部以南に多い。辺心材は、淡黄褐色、心材は褐色、都くに暗緑色の縞が出る。横断面において導管孔が年輪と関係無く、ほぼ平等に配列する、いわゆる散孔材の一つ(マカンバ、ブナ、カツラなども同様)。材質はやや重硬で、肌目はやや密。きめ細かい肌あいに他の材にはない特徴がある。割裂しやすく、加工は容易で、反り、折れ、曲がりも少ない。造作材、家具、楽器などに用いられる。 |
 18.真樺「マカンバ」 国産・広葉樹・カバノキ科 マカバ、ウダイカンバとも呼ばれる。カバ類には他にダケカンバ、ミズメ、シラカバなどがある。北海道から本州中部にかけて分布。辺心材の境は一般に明らかで、辺材は白色、心材は淡紅褐色。材質は重硬で肌目はやや密。加工性、乾燥性は比較的良い。ヤマザクラの代替材として使われることが多い。床板、敷居、家具、合板、などに用いられる。ナラ、タモ、ブナとともに家具材の一般的なものといえる。 |
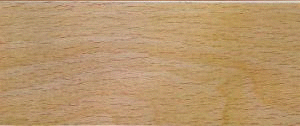 19.ブナ 国産・広葉樹・ブナ科 北海道西南部から九州にかけて分布。辺心材の区別は明らかでなく、全体に淡横白色〜淡紅色を呈す。しばしば褐色の疑心をもつ。重硬で肌目は密。変色、腐食を起しやすく、歪み、狂いも出るが、人工乾燥、防腐処理などの技術進歩により、床板、家具、合板などに用いられることが多くなった。加工性、表面仕上の良さをいかして、曲木に使われることもある。また、表面が平滑なので木地を見せない塗装下地として好まれる。 |
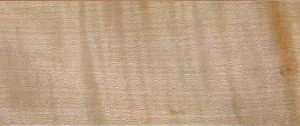 20.板屋楓「イタヤカエデ」 国産・広葉樹・カエデ科 概ね全国に分布する。辺心材の区別は明らかでなく、帯紅白色〜淡紅褐色を呈す。繊維の屈曲が著しいものは縮れ杢、波杢を示し、また特有の絹糸光沢を表わす。材質は硬軟中庸で、靭性がある。一般的な材というよりはむしろ銘木材といえる。 |
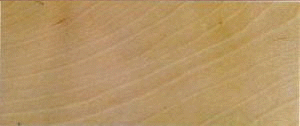 21.橡「トチノキ」 国産・広葉樹・トチノキ科 北海道南部以南の全国に分布する(九州は少ない)。同様の西洋トチノキはいわゆるマロニエで、ヨ−ロッパで広く用いられている。辺心材の区別は明らかでなく、帯紅黄白色〜淡黄褐色。波杢、縮れ杢、班杢などの杢が現れれることがあり、絹糸光沢を示す。板目面での著しいリップマ−ク(さざ波模様)が特徴。家具,楽器、茶卓、菓子鉢、杢目を生かして合板などに用いられる。 |
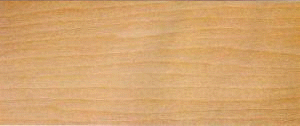 22.桂「カツラ」 国産・広葉樹・カツラ科 ほぼ 全国に分布する。辺心材の区別は明らかで、帯緑黄白色、心材は褐色。材質は硬軟、緻密で、靭性があり、反りにくい。加工は容易だが、保存性は良くない。装飾材、合板、家具などのほか、製図板、彫刻材、鉛筆、和裁板、碁、将棋盤などに用いられる。樹皮は、尾根葺材料に使用される。 |
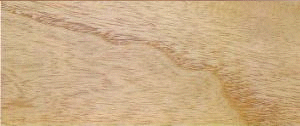 23.桐「キリ」 国産・広葉樹・ゴマノハグサ科 東北地方を中心に植栽されているが、近年は中国、アメリカなどからの輸入量が増加している。辺心材の差はなく、くすんだ白色または帯褐色、ときに紫色を帯びる。日本産の木材では最も軽く、肌目は粗で加工は非常に容易。吸水性、吸湿性が小さく、収縮膨張も少ない。生長の早いことでも知られる。たんすなどの家具類、琴などの和楽器、箱材、下駄などによく用いられる。 |
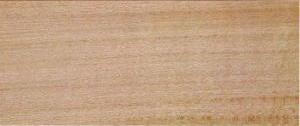 24.シナノキ 国産・広葉樹・シナノキ科 ほぼ全国に分布する。同じ科にオオバボダイジュがあり、シナノキをアカシナ、オオバボダイジュをアオシナとも呼ぶ。辺心材の境はやや明らかではなく、辺材は淡黄白色、心材は淡黄褐色。材質は硬軟、緻密で木理は、通直。保存性は小さいが、加工・乾燥が容易。多くは合板用材、塗装下地用材で、その他に鉛筆、割箸、マッチの軸、テレビ・ステレオのキャビネットなどに用いられる。 |
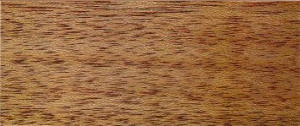 25.レッドラワン 輸入・広葉樹・フタバガキ科 ラワンとはフィリッピンに産するフタバガキ科の軽軟な材の総称である。色調が濃く比較的重硬なものをホワイトラワン類と呼ぶ。レッドラワンは、ルソン、レイチ、ミンダナオ各島などに産する。辺材は帯赤白色、心材は桃色、桃褐色。材組織は均一、木理交錯、肌理は粗い。加工は容易だが狂いやすい。装飾材、建具、家具、合板などに用いられる。 |
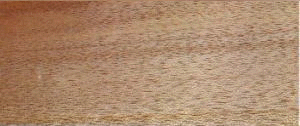 26.ホワイトメランチ 輸入・広葉樹・フタバガキ科 メランチと呼ばれるものは、材の色調によってレッド、ホワイト、イエロ−などと区別されるが、材の質としては概ね同様である。メラピ、マンガシロも同類である。タイ、ビルマ、インドネシア、フィリピンなど広い地域に産する。辺心材の差は明らかでなく、心材は淡黄色〜淡横褐色。木理交錯、肌目は粗。材中に珪酸塩(シリカ)を含み、鋸の刃に悪影響を及ぼす。造作、家具、合板などに用いられる。 |
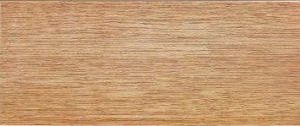 27.メラピ 輸入・広葉樹・フタバガキ科 ホワイトメランチと同類の材で、インドネシアでは、ホワイトメランチ、ボルネオ島サバではメラピと呼ばれる。また、マンガシロはフィリピン産のものをさす。ざいの色調・性状はホワイトメランチとほぼ同様で明確な区別はつけにくい。また、用途も概ね類似している。ラワン材とメランチ類は南洋材の双璧といえ、マンガシロ、メラピを含めると輸入南洋材の過半を占める。 |
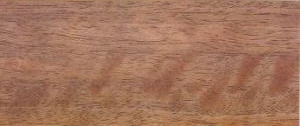 28.ニャト− 輸入・広葉樹・アカテツ科 東南アジア、ニュ-ギニア、ソロモン諸島などに分布する。マレ−シア、インドネシアでニャト−、フィリピンでナト―と呼ぶ。辺心材の境はとくに明らかではなく、心材は桃色、赤色、赤褐色、辺材はそれよりも淡色である。製材・加工は容易で、ラワン類、メランチ類と同様の用途に用いられる。 |
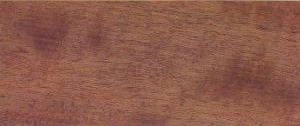 29.マコレ 輸入・広葉樹・アカテツ科 サペリと並び、アフリカ材の代表といえる。ナイジェリア、コ−トジポア−ルなどギニア湾沿岸諸島に産する。材の色調は赤褐色の者が多い。耐久性に優れる。目のつんだマホガニ-に似るが、マホガニ−より濃色で重硬である。家具、キャビネット、室内装飾、工芸細工などに用いられる。 |
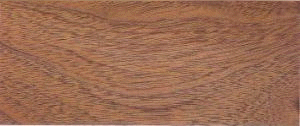 30.サペリ 輸入・広葉樹・センダン科 ギニア湾沿岸や東のビクトリア湖方面に分布する。材の色調は暗赤褐色〜紫褐色。木理が交錯するので柾目面にリボン杢が現れる。重硬で狂いが少ない。新鮮な間は針葉樹材に似た香気がある。耐久性はあるが、虫害に弱い。造作、家具、キャビネット、装飾、楽器、彫刻などに用いられる。 |
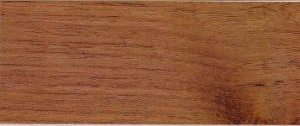 31.チ−ク 輸入・広葉樹・クマツヅラ科 インドネシア、マレ−シア、タイ、ビルマなどに産する。日本への輸入は素材ではビルマ、製材・加工材ではインドネシアからのものが多い。辺心材の色調差は明らかで、辺材は黄白色、心材は産地によってかなり差があり、金褐色、濃褐色などを示し、しばしば濃色の縞を持つ。耐久性にすぐれ、狂いも少ない。世界の最高級材の一つ。家具、キャビネット、造作など高級なものに賞用される。 |
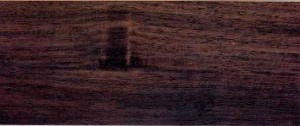 32.ロ−ズウッド 輸入・マメ科 東南アジア産、南米産、アフリカ産のものがある。インドネシア産は、インデアンロ−ズウッドとも呼ばれ、いわゆる紫檀は厳密にタイ、インドシナに産するチンチャン指す。最近ではインドネシア産は稀少な材になってしまった。南米ではブラジリアンロ−ズウッド、ホンジュラスロ−ズウッドなどがある。色調は概ね赤紫褐色で黒色に近い縞をもつ。重硬で耐久性大。家具、装飾、工芸、楽器などに用いられる。 |
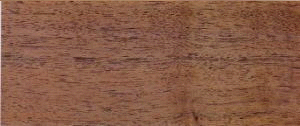 33.ウオルナット 輸入・広葉樹・クルミ科 北米から輸入される広葉樹で、ブラックウオルナットとも呼ぶ。米国東部のマサチュ−セッツからフロリダにかけて分布。辺材は灰褐色〜黄褐色、心材は褐色〜紫褐色。加工性・保存性がよい。チ−ク、ロ−ズウッド、マホガニ-などと並んで重要な装飾用材で、主に突板にして使うことが多い。家具、造作、装飾、キャビネットなどに用いられる。 |
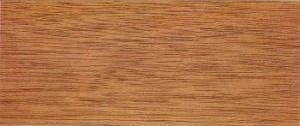 34.マホガニ- 輸入・広葉樹・センダン科 いわゆる南米材とと呼ばれる樹脂の中で最も代表的なもの。中南米各地に産しあるいは植栽も進められている。色調は淡褐色〜桃褐色〜暗褐色で金色の光沢がある。重硬・緻密でリップマ−クを持つ。装飾用材として賞用され、美しさばかりでなく、加工性、耐久性にすぐれ、狂いも小さい。一見すると、ラワン類、メンチ類と区別がつきにくい。高級家具、キャビネット、楽器、彫刻、工芸などに用いられる。 |